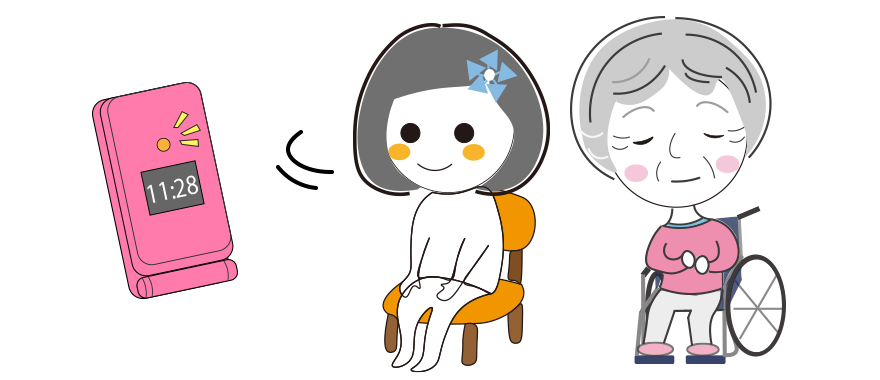
大脳皮質基底核変性症|親のスマホ(携帯)における介護の工夫
先日、母の携帯電話(折りたたみ式)が光り、メールが届いたことがわかりました。
「どうせ迷惑メールだろう」と思いつつ開いてみると、件名には「昨日から何度も連絡しています山田」とあります。
まるで本当に知り合いのような書き方で、一瞬、「母なら返信してしまうかもしれない」と思ってしまうほど、友人っぽい雰囲気でした。
差出人のメールアドレスが登録されていないことから、迷惑メールと判断し、それ以上は読まずに携帯を閉じました。
思い返せば、今から2年ほど前、母の友人を名乗る人物から留守電が入っていたことがありました。
内容からして実際に友人だったように思えたため、すでに携帯を自分で操作できなくなっていた母に説明し、私が代わりに要件を聞くことになりました。
今回のメール着信を知らせる光を見て、ふとそのときのことを思い出しました。
きっと母にとって携帯電話は、私との連絡手段というだけでなく、「世界とのつながり」を持ち続けるためのお守りのような存在だったのだと、改めて感じました。
大脳皮質基底核変性症(CBD)の進行とともに、親が使うスマホや携帯電話との関係にも時間の経過とともに少しずつ変化が現れてきます。
このページでは、母の症状の進行を振り返りながら、介護する側がどのような配慮をすべきかを記録していきたいと思います。
- 1.使い慣れたスマホが「わからないもの」になっていく
- 2.見えるはずの画面が「見えなくなる」ことも
- 3.いつでも直接連絡できる方法に勝る安心感はない
- 4.携帯(スマホ)は、親が築いた「つながり」の記憶でもある
- まとめ
1.使い慣れたスマホが「わからないもの」になっていく
大脳皮質基底核変性症(CBD)が進行すると、片側の手足がうまく動かなくなる「運動障害」が現れます。
その影響で、スマホを片手で持てなくなったり、指先が思い通りに動かず文字がうまく打てなかったりと、日常の操作が困難になっていきます。
さらに、認知機能の低下も重なると
「ロック解除の方法がわからない」
「メールの返信のやり方を忘れてしまった」
「この前教えたことがすっかり抜け落ちている」
といった状況が、昨日までは普通にできていたにも関わらず、日常的に起きるようになります。
私たちにとっては簡単な操作でも、本人にとっては複雑で、頭の中が混乱してしまうほど難解なものになってしまうのです。
母が運動障害の症状を頻繁に訴えるようになったのは、診断から1年半ほど経った頃でした。
ちょうど施設に入所して1年近くが経ち、世の中はコロナ禍の真っ只中。
面会も自由にできなくなり、施設の中の様子を知る手段が限られていた時期です。
そんな中、母が送ってくれた短いメールの文面から
・コロナには感染していないこと
・元気に過ごしていること
・外部のサービスや訪問者がほとんど来られない状態にあること
・手の不自由さから電話は難しいが、メールなら少しずつできること
など、さまざまなことを知ることができました。
母自身、「メールを書くのはすごく時間がかかって疲れるけど、不思議と夢中になって、あっという間に時間が経っちゃうのよ」と、前向きに話してくれたことも印象に残っています。
今では寝たきりとなり、当時のようなやり取りはもうできませんが、その頃の母の姿が今もエピソードとともに蘇ります。
面会ができたとき、母はよくこう話していました。
「朝方にメールの着信音が鳴って、びっくりして飛び起きるのよ」
「ワン切りの電話も鳴って、心臓が飛び出そうだったわ」
また、「こんなメールが届いたの。どうやら間違えて私に送っちゃったみたいなのね。教えてあげなきゃと思って」と話すこともありました。
おそらく、何通かは本当に返信していたと思う足跡があります。
そのとき私は、「母が前向きに関わろうとしているんだ」と、どこかのんきに受け止めていました。
今から6年以上前のことなので、当時は今ほどフィッシング詐欺や迷惑メールが社会問題化しておらず、危険意識も今ほど高くなかったのです。
ですが、現在の状況を考えれば
・スマホや携帯に使用制限を設けておく
・操作がうまくいかなくても「ゆっくりでいいよ」と安心させる
・リハビリのように、休みながら使い続けるよう促す
・急ぎのときは無理に持たず、近くに置いておくだけでいいと伝える
といった、具体的なルールづくりや声かけが、介護する側に求められる配慮だと思います。
母の携帯はスマホではなく、いわゆる「ガラケー」だったことも、結果的には良かったのかもしれません。
ネット検索をする習慣がなかったため、悪質なサイトに誤ってアクセスするリスクも低く、ある意味で安心できる環境だったのだと思います。
2.見えるはずの画面が「見えなくなる」ことも
大脳皮質基底核変性症(CBD)では、視力そのものではなく、「目の動き」が制限される症状が現れます。
見たい方向に目を向けることが難しくなったり、視界が狭まったり、ピントが合いづらくなったりするのです。
そのため、小さなスマホ画面をじっと見つめることが苦痛やストレスにつながることがあります。
母が「眼が見えにくくなってきた」と口にしたときのことを、私は今でもはっきりと覚えています。
その当時、私はまだこの病気に「視覚に関わる症状がある」ということを知りませんでした。
「右手が痛い」「右足が動かない」「また転んだ」など、明らかに目に見える症状に気を取られていたのです。
大脳皮質基底核変性症には多くの症状がありますが、特に片側に強く現れる運動障害や、手足の違和感といった典型的な症状ばかりに意識が向いていたのだと思います。
その頃、母は転倒を繰り返していました。
顔から倒れて顔の半分が腫れたり、机の角に目をぶつけて充血したり。
「見えにくい」と言われても、それが視覚の問題ではなく打撲などによるものだと思い込んでいたのです。
だからこそ、母が「目が見えない」と言ったとき、「え?どういうこと?」と繰り返し聞き返してしまいました。
そのとき母は、「一点を見つめられなくなった」「携帯の画面をずっと見ていられなくなった」と言っていました。
でもその意味を私はすぐには理解できず、ずいぶん後になってからようやく思い出すことになります。
それは、難病の会で出会ったある人が、「PSP(進行性核上性麻痺)の初期は、眼が見えにくいとよく訴えがあって、メガネを作り直すんだけど、また見えにくいと訴えがあって。新品に近いメガネがいくつもある。」と話していたのを聞いたときのことです。
CBDとPSPは症状が似ていることがあり、ようやくあのとき母が言っていた「見えない」の意味が腑に落ちました。
その頃から、母が携帯を使う頻度はどんどん減っていきました。
「どうしても眼が見にくい」という言葉とは裏腹に、がんばりやの母のことなので、何とかやっていたと思います。
でも携帯の画面を見ることが自分の努力だけでは何ともならないということに絶望し強くストレスを感じていたのだと思います。
この経験から私が学んだのは、連絡手段をスマホや携帯に依存しない生活スタイルを、早いうちから準備しておくことの大切さです。
そして、施設に入所する場合には、施設との信頼関係をあらかじめしっかり築いておくことも重要です。遠距離介護の場合は、使い慣れた家の電話で話す、近所の人とのパイプを作っておくなど。
ただし、一つ忘れてはならないことがあります。
それは、「施設側からの連絡だけで物事を判断しないこと」です。
携帯を使えなくなったことで、私と母との直接的なコミュニケーションは減り、代わりに施設からの報告が主な情報源になっていきました。
その頃から、私は施設のスタッフから母の『至らなさ』や『困った様子』を頻繁に聞かされるようになりました。
「この施設に長くいてもらうには……」と、何度も言われ、私はそのままの言葉を母に伝えてしまったことがあります。
今でも、それは私の大きな後悔の一つです。
後になって、母の話をゆっくり聞いてみると、ちゃんと理由があったのです。
例えば、こんなやりとりがありました。
施設側:「お母さん、また転倒されました。私たちは「コールボタンを押して」と何度も言っているのに、それを無視して勝手に動かれても困るんですよ。それで転んだって言われてもね。」
その話を私はそのまま母に伝え、「この施設に居たいんだったら、ちゃんとルール守らないと」と言ってしまいました。
それはもう、娘の言葉ではなく、施設側の言い分そのままでした。
でも母はこう言いました。
「コールを押しても来てくれないんだよ。トイレに行きたいと思ってから10分も誰も来なかったら、粗相しちゃうでしょ。来ないから『忙しいのかな』『迷惑かな』って思って、自分でやるしかないって思ったの。オムツをされても、オムツの中ではできないんだよ、したくないよりできないんだよ。」
私は、そのとき初めて気づきました。
私が本当に向き合うべきは「施設の都合」ではなく、「母の思い」だったのだと。
それから私は母の代弁者になることを意識することにしました。
関連記事はこちらから…大脳皮質基底核変性症|闘病記|転倒
話が少し逸れてしまいましたが
大脳皮質基底核変性症の症状によって、スマホや携帯が使えなくなる時が必ず来るという前提をもって、介護者自身が迷わずに対応できるように準備しておくこと。
それが、今、母の携帯を前にして思うことです。
3.いつでも直接連絡できる方法に勝る安心感はない
施設介護や遠距離介護の場合、スマホは親との命綱のような存在になります。お互いがすぐに連絡を取れるというだけで、親にも介護者にも安心感があります。
それはそうと、母が自分で携帯を操作できているときには
「よく電話がかかってくる」
「こっちの時間を考えないで連絡してくる」
「なぜか怒っている」
「泣き言ばかりで聞くのも嫌になる」
など私は思ったものです。
母の立場にたって考えるのは、大脳皮質基底核変性症でない私が考えるということであって、想像でしかないのですが、独りでいる母にとって、よくわからない病気になり、どんな内容であっても私と繋がること自体が安心だったのだと今さらながら思ったりもします。
でも携帯って私との繋がりだけではありません。
そこは充分介護者が工夫を求められるところです。
あるとき、母がテレビショッピングを見て電話をかけて商品を購入していたことがありました。
→ひょえー!私のために買ってくれたとはいえ…高額な商品でなかったことが幸いでした。
別の日には、熱心にメールをしている母に「お友だちとメールしているの?」と聞くと「この人、私と一緒で困っているみたいなの。」
→おおおおっ!その人はいったいどこの誰?案の定、その連絡先から怪しいメールがジャンジャンやってくるようになりました。
昔は家に電話がかかってくると、どんな相手にもきちんと応対していた母。
携帯でも同じように、礼儀正しく対応しようとしていたのかもしれません。
だからこそ、連絡先にない知らない番号はブロックするなどの工夫も、介護者には求められます。
4.携帯(スマホ)は、親が築いた「つながり」の記憶でもある
施設に置いてある母の携帯をたまに手入れしていると
眠れない夜、母は友人とメールで語り合っていた過去のメールにも出合います。
やっぱり、携帯は、家族だけでなく外の人とつながるための大切なツールでもあったのです。
世代によっても、進行具合によっても、携帯(スマホ)の扱いは異なります。
事件も多い昨今ですが、私は母から携帯を取り上げなくて良かったと思っています。
いま、母が携帯を使うことはできません。
母は誰かに連絡したいのかもしれません。
現在失語となってしまった母は私にそれを伝えることもできません。
この携帯は母の繋がりから連絡が来たときに出番があります。
たしかに母が過ごしてきた時間が詰まっている証として存在しているのかもしれません。
私は携帯を「お休みタイマー」に設定し、母の部屋にそっと置いてあります。
まとめ
大脳皮質基底核変性症の介護では、親がスマホを使えなくなる未来を見越して準備しておくことが大切です。
頭がしっかりしている場合もある大脳皮質基底核変性症ですが、運動障害や視覚に関わる障害が出てくる可能性があるからです。
そして、携帯やスマホにこだわるのではなく、「親が安心できるつながり方」を一緒に考えていけたら、それが一番の支えになるのかもしれません。
他の記事はこちらから…介護記事一覧
