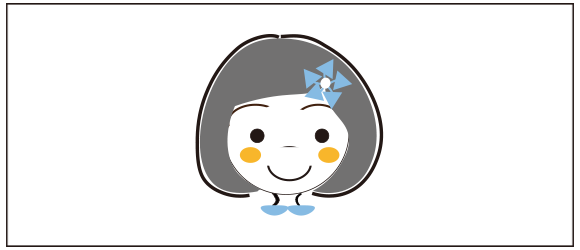
このページでは「大脳皮質基底核変性症」という難病と診断された母を介護していく中で経験した情報を記録していきます。
- このページの難病介護とは?
- 大脳皮質基底核変性症(指定難病7)と診断された母を介護する経験を記録します。
- 大脳皮質基底核変性症とは
- 主治医から教えてもらった症状は
●10年かけてゆっくり進行する
●片方の筋肉が固縮する
●片方に違和感を感じると訴えることから始まることが多い
●パーキンソン病のような症状が出る
●脳が萎縮し発見されるが診断が難しく診断名が出るまでに時間がかかる
●症状が進むと言葉を発するまでに時間がかかる
●痛みが強い
●痛みは脳が誤って感じる痛みであるため鎮痛剤が効きにくい
●原因はわからず発症人数は6000人にも満たないのではないか
●人数が少ないので統計的にどうだという判断レベルではない
など
参考までに(2022年4月時点)
大脳皮質基底核変性症(指定難病7)とは
公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター
- このページはどんな経験情報があるの?
- 大脳皮質基底核変性症という指定難病だと知ってから、まずどうしたらいいのかその当時本当にわからなかった。
この先どうなっていくのか、どうやって介護していいのか、全くわからず途方にくれたことも多々。
自分が「知りたいと思ったこと」という判断軸で情報を記録します。
中にはとりとめのない日常の記録もあります。
親の介護が始まったのは10年ほど前。
どちらかというと介護が始まるのが早かったのかもしれません。
というのも病院や施設の人から「お父さんはまだお若いのね」
とよく言われたからです。
まわりの友人や知り合いには同じように親を介護をしている人がおらず、
また今のようにインターネットが完備されていなく
情報の見つけ方は人づて情報か病院の診察の一瞬の時間だけでとても少なく、常に手探りな状態でした。
まずは父親の介護からスタート。
それに併せて母も精神的にどんどんおかしくなりました。
ずいぶん先に母は難病指定の病気であることがわかりました。
介護スタート時点では、会社は「介護」に対してそんなに寛容ではなく、社内でも「介護休暇」「介護休業」などの認知度が少なく、またそれに応じた社内制度も引かれていない状態の中、「介護で休む」という理由に対して同僚からは遠巻きにされ、腫れ物に触るかのような距離感が生まれ、理解を得られない状況が続きました。
今思い起こすと、「介護スタート」時点が一番しんどかったように思います。
抽象的に介護を山登りに例えれば、いきなり急勾配の上り坂から始まります。
それも濃い霧の中を息つく暇もなく。
濃い霧は不安をどんどん増幅させます。
「もしかしたらまた普通の生活に親は戻れるのかもしれない」などと勝手に期待しながら、行く先もわからない霧の中を進みます。
「しんどい」と感じるのは少し先になってからです。
ほんの一息つけたのは「親の介護」が常態化しその現状に慣れてきたときか、
いわゆる要介護度3を超えて施設入所が決まったとき、
またはお金の算段ができて、ある程度の親の介護の先が見えたときでした。
とはいえ、あくまでも一息ついても、まだ山登り最中です。
足元には石ころがあって躓いたりそのまま転んだり、たまに歩きやすい山登りの時もあります。
あるとき病院の先生に
「ひと昔前は自宅でお世話をしていたのである程度の時間が過ぎると介護に終わりがきたのだけど、
今は施設に入所したり専門的なサービスをしてもらうので「介護」という時間がとても長くなったね。
先が見えない状況にいる時間が本当にみなさん長くなった。」と言われました。
そのときからずいぶん時間が経つのですが、確かにまだ介護は続いています。
私は両親の介護を経験しているのですが、山がふたつ。別々ではなく山が重なり、山の上の山があったというような状態かなといまの時点から振り返るとそんな例えが適当なのかもしれません。
「介護」を通して、両親と私のことを思い出すきっかけもあり、またまた「老いる」ことについて考えたり、「介護はしんどい」というだけのものではないということがわかりました。
人それぞれの介護がありますが、「難病介護」を記録します。
◆難病介護記事一覧はこちら
