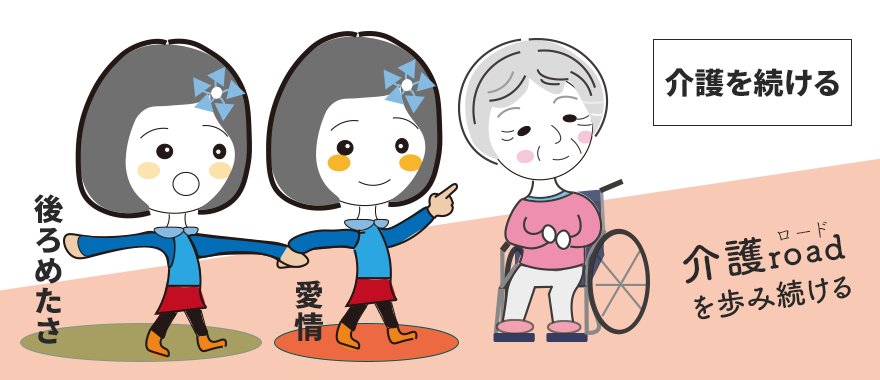
介護を続ける理由は「愛情」だけじゃないー介護を支える心のチカラ(罪悪感、後悔)
ある高齢の男性が、毎日のように施設に入所している奥さんのもとへ通い、散歩に連れ出す姿がありました。
その姿は、長年連れ添った伴侶への深い愛情を感じさせるものです。
しかし、ある日その方と会話をする機会があり、「今まで迷惑をかけたので罪滅ぼしというところもあります」とおっしゃいました。
あるときには「苦労させられたと思っていたら実は脳の病気だったことがわかって」と車いすの旦那さんの横で静かに寄り添う奥さんが「恨むくらいのこともあったけど、でもなんか仕方がないか、逆に悪いことしたなって思って協力しています」と言葉を続けられました。
これらの言葉を聞いたとき、介護を続ける人の心のチカラについて深く考えさせられました。
人は単に「大切な人を大事にしたい」という純粋な気持ちだけで介護を続けられるものなのか、それとも、「後ろめたさ」や「償いの気持ち」があるからこそ、人は献身的になれるのか。
このページでは、介護を続ける人の心のチカラについて考え、「後ろめたさ」や「償いの気持ち」が介護にどう影響を与えるのかを考え記録します。
1.介護を続ける理由は「愛情」だけじゃない?
介護と聞くと、愛情が最も大きな動機であると思われがちです。
確かに、家族やパートナーへの深い愛情が介護を支える要素であることに疑いはありません。
しかし、それだけでは長期にわたる介護を続けるのは難しいこともあります。
実際、介護をしている人が
「今まで迷惑をかけたから」
「もっと親孝行をすべきだった」
「若い頃に世話になったから、その恩返しをしたい」
という思いを抱えていることを知る場面に出合います。
つまり、過去の行動への「後ろめたさ」や「償いの気持ち」や「後悔」が、介護を続ける上で大きな影響を持っているのかもしれないとその人たちの言葉から感じています。
では自分はどうなのかと自身を振り返ってみると、純粋に母のことを大切にしたい気持ちだけではないといえます。
以前の記事に母に対してやってきた行動への後悔を書いています。
とくに大脳皮質基底核変性症|水分摂取(内部リンク)
の中で
「病気だなんて知らなかった私は、
母との関係悪化に悩み、
母が辛くて苦しんでいることよりも、
母の異常行動や性格変化から受ける自分の苦しみを
存分に感じてしまい、寄り添えなかったからです。」
と書いています。
2.「後ろめたさ」が人を優しくする?!
〜人は後ろめたさを抱えるほど優しくなれるのか〜
という問いはなんだか薄情な気がしますが、実際に、周囲にいる介護者が
「もっと若いときに親孝行しておけばよかった」
「もっと元気なときから大事にできることがあったのでは」
「昔に苦労させたから」
といった後悔の念を口にする場面に出合えばそう感じるのも合点がいきいます。
心理学的にも、罪悪感は行動の動機づけとなることが知られています。
人は過去の行動を振り返り、それを修正したい、埋め合わせをしたいという気持ちがあると、より他者に対して優しくなれるようです。
介護する側、される側の関係性に注目すると、介護をする必要が出る前は対等だったのが、介護しなければならなくなると関係性に変化が出てきます。
例えば親子の場合、私の例をとれば、親の意見の方が強いことが多いし、自分の意見を主張できるときにはそれを叶えてあげなければいけない(解決しない)と思う状況に置かれています。
それが介護の状態が進み、関係性の立ち位置の強弱が反転すると、介護する側にコントローラーがほとんど渡るわけです。
そうなってくると、それが介護される側の意見や考えでなくなり介護する側の操縦力量に委ねられ、介護する側がすべてを背負わなければならなくなります。
そうなると自分が体験したい喜びを相手に体験させたいという願望が出たり、もしかすると気づかないうちに世間体への配慮もあり、介護者が自分自身の過去を振り返り、それを埋め合わせする機会に多く出合うようになるからなのかもしれません。
この複雑に絡み合った「後ろめたさ」こそが、「優しさ」の正体であり、粘り強く介護を続けるエネルギーになっていることが多いのかもしれません。
3.介護をする人が抱える葛藤
ただし、「後ろめたさ」があるからといって、必ずしも良い介護ができるわけではありません。
罪滅ぼしの意識が強すぎると、自分を責めすぎたり、無理をしてしまったりすることもあります。
介護は時間的にも労力的にも自己犠牲的な精神の上に成り立っているからかもしれないと思うからです。
24時間を自分のことに関することに使う時間とそれ以外に使う時間に分けて考えたことがあるのですが
自分が生活を送る上で家事や育児などは自分の時間と捉え、自分が生きていくための仕事も然り、睡眠や食事なども自分時間。
母にまつわること、例えば施設への訪問、病院付き添い、役所周りの申請、必要な買い物、ケアマネさんとの連絡などをそれ以外とした場合、意外にも多いことに気づきます。
介護はもはや私の生活の一部だと思っているにも関わらず、意外にも多くの時間と労力を割いているなと感じることは反する気もするのですが。
そうやって自分を見つめ直さないと、自分の生活を犠牲にしてしまう人も少なくありません。
とくに介護離職をしなければやっていけないかもと感じる場面もあったことを考えると、仕事も辞めて介護に専念しなければ親不孝者と感じたこともあります。
実際に母にそう言われたこともありました(母にとっては不安しかなかった時期だったので)。
大切なのは、「後ろめたさ」を感じること自体は自然なことであり、「後ろめたさ」が介護をするきっかけとなること自体悪いことではないのです。
でも、その気持ちに押しつぶされないよう、適度な距離感を保ち、周囲の支援を受け入れることが重要ですね。
4.介護を続けるための心の持ち方
介護を続ける上で大切なのは、愛情だけに頼らず、時には「後ろめたさ」も受け入れながら、そして自分自身を責めすぎないことです。
「過去は変えられないが、今できることを大切にする」
→ 過去の後悔を完全に消すことはできませんが、いま目の前にいる大切な人に寄り添うことで、まだ間に合う!その後悔への思いを少しずつ和らげることができます。
「完璧な介護を目指さない」
→ 介護は長期戦です。
すべてを自分一人で抱え込もうとすると、心も体も持ちません。
周囲の人、専門家の力を借りながら、持続可能な形で関わっていくことに目を向けることが大切です。
「介護を通じて自分自身を成長させる気概でいる」
→ 介護は苦しいことも多いですが、同時に自分自身を見つめ直し、より深い愛情や思いやりを育む機会でもあります。
人の立場に立って生きることを考えることは、介護する機会を与えられたものだけの特権でもあると私は思います。
人生100年時代と言われるこの世の中で、自分の年齢の重ね方や考え方などへ変化が出てくるのではないかと思う次第です。
まとめ
介護を支える心のチカラは、単なる愛情だけではなく、「後ろめたさ」や「償いの気持ち」が大きく影響していることがわかります。
過去の行いに対する後悔があるからこそ、人はより優しくなれるのかもしれません。
しかし、その気持ちが過剰になると、介護をする側が疲れ果ててしまうこともあります。
だからこそ、「後ろめたさ」を否定せず受け入れつつ、自分自身の心と体も大切にしながら介護を続けることが、自分へのこれからの人生にも役立つことと考えながら自分の人生も充実させる鍵となるでしょう。
介護をする人が「後ろめたさ」を抱えるのは決して悪いことではありません。
それは、相手を強く想うからこそ生まれる感情であり、それ自体が「優しさの証」だったり「介護への粘り強さ」へのきっかけになったり、介護を支える心のチカラなのかもしれません。
他の記事はこちらから…介護記事一覧
