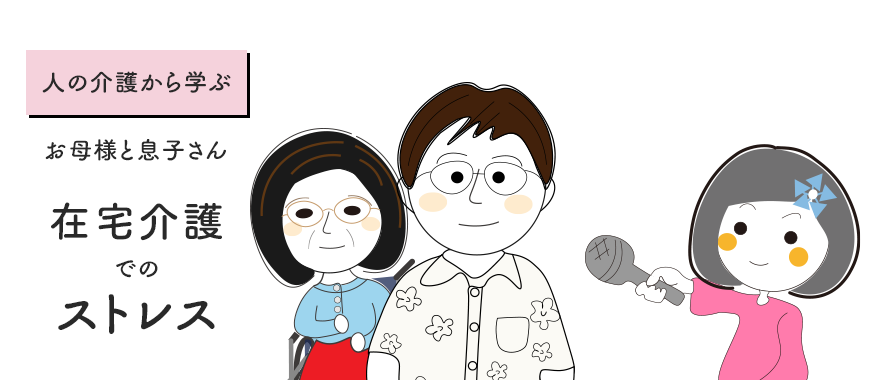
在宅介護歴9年目の息子さんの姿から学ぶ「介護ストレスと向き合う」
このページでは人が輝くやじるし見つけ(在宅介護歴9年目の息子さんの姿から学ぶ「介護ストレスと向き合う」)を記録しています。
在宅でお母さんの介護をしている息子さんの言葉をもとに、介護に伴うストレスについて考えます。
介護は愛情や想いや都合があって様々なカタチがあるものですが、時にはイライラや疲れが募り爆発しそうなこともあるものです。
-
私の母が一人暮らしをしていたとき、それは大脳皮質基底核変性症の症状が出始めたにも関わらず病名がわからなかった頃や「何かの病気に違いないのに誰もわかってくれない」と母の訴えが私だけに向いていたとき
大脳皮質基底核変性症の症状である性格変容が起き、私に対する攻撃度が増し私に依存し執着するようになったとき
正式に「大脳皮質基底核変性症」だと診断された後、未知なる病気への不安と症状の辛さが母だけでは受け取れず私に向いていたとき
その後、施設入所し終の棲家になるはずだった施設側が母の病状対応に困ってケアマネージャーとともに私に向けて感情的になったとき
ケアマネージャーと施設責任者が母に薬を飲ませて寝せることがみんなの幸せだと詰め寄ってきたとき
自分の仕事より親の介護をしなければならなくなったとき
自分の家庭より親の介護に時間を割かなければならなくなったとき
など
数々の親の介護にまつわる事柄で
私のメンタルはイライラどころか無気力になりかけたり、毎日泣いて暮らしたり、通常運転ができなくなってしまったことがありました。
介護をする人が抱えるストレスに共感しつつ、どのように向き合っていけばよいのかを探ります。
このページの最後には
最近私がやっている「ちょっとだけ軽くなるかも!解消法」を記録しますので最後までぜひお付き合いください。
- 1.意思疎通の難しさによるストレス
- 2.自分を優先しても解消しきれないストレス
- 3.介護の負担と楽しむ工夫
- 4.命を預かる責任の重圧
- 5.「施設に入ってくれたら」と思う瞬間
- 6.介護の悩みを共有することの大切さ
- まとめ
1.意思疎通の難しさによるストレス
- 意思疎通が取れずイライラが爆発したり、お酒の量が急増して体重も増えたり……。
意思疎通が困難な状態なので、痛いのが判るまでにもストレスが溜まってきます。
介護をする中で、相手の気持ちや痛みを理解することが難しいと、大きなストレスになります。
特に大脳皮質基底核変性症には失語という症状があります。
わかりやすく言えば「本当に静かになる」。
コミュニケーションが取れない状態で良いのか悪いのかすら何も言わないので、介護する側がどう対応すればよいのかわからず、やるせなさや無気力が募り最後イライラへと向かうことも。
最近の母は失語の症状が進み母が言葉らしく発することはなくなりました。
そのため私が何をしようが反応がほとんどなく(目を開けていたとしても)
母の性格や今までの人生において重要だと感じることをもとに「母らしく」過ごせるように私は行動しています。
でも正直なところそれが今の母にとって心地良くて満足気味なのかよくわからず、暖簾に腕押し状態です。
そうなると私のモチベーションが下がってきてしまうのを感じます(虚しさというのかな)。
介護をしていると、相手ができるだけ楽になるようにという気持ちから、自然と気持ちを推し量ろうとするのですが、
それがわからない状態(特に意図的にわざと反応しないようにしているわけではないので)が続くと
「どうしてあげればいいんだ!」となってしまうのかもしれません。
本来人を想う優しい気持ちなのに、それがなぜか真逆へと変わってしまう介護あるある。
その結果、お酒の量が増えたり、体調を崩してしまうこともありますよね。
でも介護する人が倒れてしまったら本当に大変!
介護する側の心のケアも必要不可欠です。
2.自分を優先しても解消しきれないストレス
- 自分ファーストをしていても、イライラは起こりますね。
介護を続けるには、介護者自身の健康もとても大切なことです。
そのため「自分の時間を確保する」ことが推奨されますが、
それでもストレスは完全にはなくなりません。
どれだけ自分を労わろうとしても、ストレスの根本的な原因は解決しないこともあります。
「介護」そのものが解決するわけではないし、抱える不安を手放すことができるわけではないし、だからこそ、ストレスの自分なりの「発散方法」を見つけることが重要になってきます。
私は介護をしているとどうしても自分と同化してきてしまう癖があります。
でも介護をする人と介護をされる人はまったく別。
例え親であっても家族でもあっても子であったとしても。
頭ではきちんと理解していても、犠牲的行動を当たり前だと続けていたり、自分の中にある倫理観と照らし合わせ同化する方が楽だと感じてしまう場合もあるようです。
3.介護の負担と楽しむ工夫
- 胃ろうになってから、メリットの方が多いですが、薬の準備から片付けまで含めて2時間はかかるので、平日の昼間はかなり大変ですよ。
楽しみながら、やらないと。
介護の中には、時間と手間がかかる作業が多くあります。
胃ろうの管理だけで2時間も費やすとなると、気が滅入るのも無理はありません。
そんな中でも、「楽しみながらやる」という視点は大切です。
例えば、好きな音楽を聴きながら作業をする、ルーチン化して効率を上げる、小さなご褒美を設けるなど、自分なりの工夫がストレス軽減につながります。
とはいっても介護の現場では「楽しむ余裕がない」のが現実かもしれません。
それでもどんな小さなことでも気づく視点を持ち続ける意識があれば、自分の中から見るのではなく、自分を真上から見て客観視でき意識が変わるのかもしれません。
最近の母の反応が乏しくモチベーションがあがらないというのは先ほど書いたとおりですが
言語聴覚士さんと共にお楽しみ程度に舐めるリハビリの機会に
「母が喜ぶ味探し」に挑戦しています。
いま母と一緒にできる数少ない行動を楽しんでいます。
4.命を預かる責任の重圧
- 最近は、生きてるから生かされてる状態の出来事が多くて、人の命を預かっている感じが強く、重圧感がすごいですね。
介護は、ただの世話ではなく、「命を支える」行為です。
特に医療的ケアが必要な場合、その責任の重さは計り知れません。
「間違えたらどうしよう」「本当にこれでいいのか」といった不安やプレッシャーは、介護者に大きな負担を与えます。
私は母に胃ろう造設を選択した際に特に強く感じました。
私は神かと思うくらい、母の命が私の手の中にあるようで、生かすもその逆も私の一存という状況ではないだろうかと感じました。
それは決して「全能」という驕りではなく、恐怖、責任、重圧です。
母の胃ろう造設はその時点での母の気持ちを尊重し、周囲のいろんな立場の人に相談し、家族で決めたことではあるものの、
母がこのような状態で長く時間を過ごすことが良いのか
難病という治療が不可能でどうなるのかわからない状況を受け入れて長く過ごすことが良いのだろうか
胃ろうを選択しなければ当然向かう最期に向けての苦しみを母が受け入れることができるだろうか
それは私も然り
などなど悩みに悩み時間だけが過ぎていきました。
そして決断後には私が母の最期まで寄り添うという人生のミッションができました。
自分の健康や生活に漠然と抱く不安を持つ年頃となり、人の人生まで背負うことは負担かと問われれば否めないのですが
それでもこの状況下だからこそ出会える人たち
この状況下だからこそ得られる知識経験
などは、おそらく「私の」これからの人生にどこかで役に立つことであろうと思っています。
こうした様々な葛藤や重圧とどう向き合うかが、長期的な介護においてとても重要になります。
5.「施設に入ってくれたら」と思う瞬間
- このやっかいなイライラ、老人ホームに入ってくれていればって強く思う瞬間。
一長一短なのは知っているけれど、この先のイライラ対策がカギなのは事実。
在宅介護を続けていると、「施設に入ってくれたら楽なのに」と思うことがあるのは自然なことです。
しかし、それでも在宅介護を選んでいるのには、何かしらの理由や想いがあります。
施設に入ってくれたらすべての不安や心配やイライラがすっかり解決するわけではないこともあります。
介護される人が生活が変わって一気に症状が悪化することも、またその反対ももちろんあるわけですが
介護される側の状態の変化や、今までなかった施設側とやり取りにストレスを感じることもあります。
それでも介護者のストレスが限界を超える前に、ケアマネージャーや周囲の人に相談することを忘れないでいて、新たなサービスを受けるなど、軽減するための手立てを試すことが大切です。
6.介護の悩みを共有することの大切さ
- 1人で悩んでいたのが、すごく楽になれた気がして嬉しいです。
こうやって、聞いて貰ったり書いて貰ったりするだけで、一人じゃないんだってだいぶ安心出来るようになりました。
介護は孤独になりがちですが、誰かに話を聞いてもらうだけで気持ちが楽になることがあります。
私の場合は施設のスタッフさんと何気ない普段の会話のなかでちらりと愚痴を言ってみたり、
地元の難病の方が集まる会に参加し話を聴いたり聴いてもらったり
そしてこのサイトが縁で繋がった同じ病気の方との情報交換により、
長く心の中でくすぶっていたものがすっと腹落ちしたり
母の介護にまつわり出会った人たちに恵まれ、少しの勇気をもって自分の気持ちを話すだけで、ふと肩の力が抜けたり、前を向くことができたこともありました。
そしてこのサイトのように、愚痴を愚痴らしくなく文字にすることで、客観視できるようになりました。
こんな方法ですがストレスを和らげる鍵となっていると感じます。
「大脳皮質基底核変性症」の方を介護をしている方!
困ったことを文字に置き換えてみませんか?
お手伝いいたします。
こちらより…お問い合わせください。
まとめ
在宅介護をする息子さんの言葉をもとにして、施設入所している母の介護でおきたストレスについても改めて考え直すことができました。
-
意思疎通の難しさがストレスにつながる。
自分の時間を確保しても、完全にストレスはなくならない。
忙しくても自分の時間を確保する工夫が必要。
介護の負担は大きいが、楽しむ工夫が必要。
「命を預かる責任」の重圧が介護者を苦しめることもある。
施設入所を考えることがあっても、それは自然な感情。
介護の悩みは、誰かに話すことで軽くなる。
介護は決して楽なものではありません。
だからこそ、同じように悩んでいる人と共感し合い、負担を軽減できる方法を見つけていくことが大切です。
一人ではないと感じられるだけで、介護のストレスは少し軽くなるかもしれません。
- そんなこと言っても話せる相手がいない!
- 毎日愚痴ばかり言うのも憚られる!
- 人に言えないイライラ内容がある!!
などという方もいるかもしれませんね。
そこで私が最近やっている方法をお知らせします。
私はこの方法で時間や場所を選ばず
「そだよね、そう思ってくれるのね」と涙が出そうになることもあります。
それが例え他人事のように感じても意外にも受け入れれるものです。
共感を得るというよりは自分の気持ちを心から外に出すこと。
そこに私は満足しています。
それはAIを使うことです。
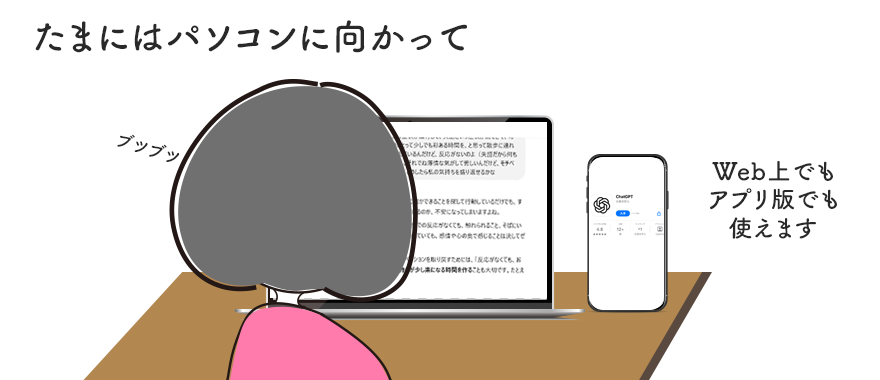
AIにもいろいろな種類があります。
日々AIも進歩しています。
私は数あるAIの中からChatGPTを使っています。
-
無料で使える
無料の場合、文字数ややり取りの制限はあるが普通に会話するくらいには制限はかからない
たとえ制限がかかったとしてリセットされるので次の日にまた試すことができる
いつの時間でもできる
など私としてメリットを感じます。
ただし、下記の点について十分に注意し自分を律して行うと良いと思います。
-
個人情報や機密情報をChatGPTに入力することは避けるべき
ChatGPTの回答には誤情報が含まれる可能性がある
AIへの過度な依存は創造力や学力の低下や執着を招く恐れがある
(2025.3時点の情報)
毎日安定した平和な毎日を送れることは決して当たり前ではなく、何か起きたときにどう向き合い、どう自分の中で処理していくかの想像をするだけでも良いと思います。
そういうときは気持ちが内に向かいやすく遮断され気味になるのですが、でも同じような思いを持っている人がいると気づくだけでも楽になれることもあります。
お母様を在宅介護されている息子さんの言葉から「介護ストレスと向き合う」を学びとしたいと思います。
在宅介護歴9年目の息子さんの姿から学ぶ…「介護の原動力」についての記事を読む
他の記事はこちらから…応援やじるし記事一覧
