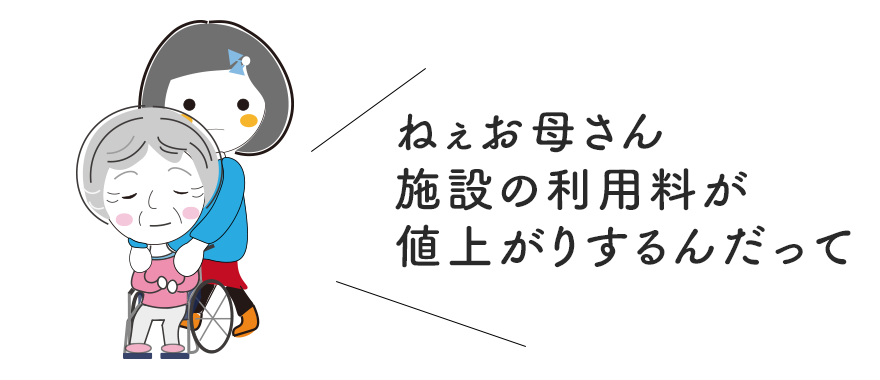
施設介護の現実|施設介護にまつわる費用の値上げ
施設介護の現実。
ある日突然届いた「施設利用料値上げのお知らせ」が、なんとか見えていた未来を打ち砕く。
封書を開けるとそこには
「9月分の請求より、5万円の値上げ」と書かれていました。
ひょえー
ご、ご、ごまんえん!
声が裏返り、小さな叫び声とともに、頭が真っ白になりました。
母のいる介護施設の事務的な用紙1枚の通知。
それは私にとって、母の病気が発覚した時と同じくらいの衝撃…いや、もっと現実的で、冷たい絶望感を伴う「第二の告知」でした。
今回は、難病である大脳皮質基底核変性症の母を介護するお金の記録。
今の世の中よくある話?!
もしかしたら、同じように介護しているどこかの誰かも私と同じような気持ちを抱えているかもしれませんね。
1.母泣く、介護の理想と現実の狭間で
母が難病であると知り、施設入所での介護が始まった時、真っ先に頭をよぎったのは「費用」のことでした。
誰しもが考えることだと思うのですが、介護は先が不透明、かつ稀な難病となれば、トータルいくら費用がかかるのか計算できません。
病気のことだけの悩みではない、それは世の中誰しもが大きな心配事になります。
母が生きていくために必要なお金。
そして母が持っているお金。
母が管理しているお金。
しっかり者の母は、それまでに入念に準備をしてきたので、母が「この施設なら入りたい」と望む施設の料金について娘の私でもとやかく言えない状況でした。
本音を言えば、それは「母が管理しているから」と主導権が母にあったから、というよりも、私が何かを言うことで、母が施設の入所を渋るようになったり、「じゃ、娘のあなたがお世話してよ」と言われるかもしれない、という気持ちの方が大きかったのかもしれません。
「在宅介護は絶対に無理」とケアマネさん始め、施設スタッフさんから言われ、その言葉に甘えて施設介護を選択してきました。
当然、母は私に面倒をみてもらいたかった、一緒に暮らしたかったという気持ちがあったことも知りながら。
でも、実際に進行していく母の病状、私が働きながら介護と両立させることの現実的な限界、そして私自身の人生のタイミング…。
全てを天秤にかけた結果、施設介護しか選択肢がなかった、が現実であって、そしてその距離感で、ここまで二人三脚でこれたのだと感じています。
施設介護にするにあたり、
「母の年金と資産で、月々この金額までなら…」というざっくりとした基準値を持つようになったのは、母の難病が進行し、母がお金の管理をすることが難しくなり、私に託したタイミング。
母とともに過ごす時間が長くなったとしても、「これくらいなら大丈夫」と月額×12か月×年数を頭の中で計算していたのです。
でも、その計算には「世の中の物価がこんなにも急激に上がる」という未来は含まれていませんでした。
コロナウィルスがくることも知らなかったあの頃、そして物価が急上昇している世の中を、あのときから描くことができるわけもなく、その甘い見通しを根底から覆すのに、今回の施設からのお知らせは、十分すぎる威力がありました。
母に悲しい思いをさせるのは忍びないのですが、言わずにいるわけにもいかず、母に話してみました。
「頭の中では、聞こえてきた話を理解しようとしている」という主治医の言葉どおり、母は「わぁー」という泣き声とも叫び声ともいえる声をあげました。
果たしてその声の真意は、想像するしかないのですが、少しして母の目に涙があることを知りました。
2.他人事ではない。介護費用「値上げの真実」
この件で、同じ施設に入所している家族の方や施設スタッフさんと話す機会がありました。
施設内には私が想像していた以上の動揺が広がっている様子です。
「他の施設だって同じだよ。世の中がこうなんだから仕方ない」
「長年連れ添った奥さんの命の値段と、お金を天秤にかけるなんてできないよ」
「私の友人が入ってる施設も値上げされていると聞いた。でも、普段の対応はこっちの施設の方が良くて、まだマシな方じゃないかと思っている」
「払えないから出なくてはと言っている人がいる」
「突然の告知でこのアップ率は他でも聞いたことがないです」
つまるところ「命とお金」
デリケートな問題です。
人件費の高騰、光熱費や食費の値上がり…施設側も苦渋の決断だったのでしょう(←文書にはそう書いてある)。
なぜ、介護施設の利用料が上がり続けているのか。
これは決して、特定の施設だけの問題ではなく、背景には、私たちにはどうすることもできない、大きな構造的要因が存在します。
最新の調査や報道によると、値上げの主な理由は3つ
1. 物価・光熱費の高騰
2. 人件費の上昇と深刻な人手不足
3. 介護保険制度の改正
数年前の「常識」は、もはや通用しません。
介護にかかる費用は、私たちが思う以上に、社会経済の波に大きく左右されるのです。
私たちが暮らしていて感じる何でも値上がりの波と同じ。
あの時立てた資金計画が、あっという間に崩れ去ってしまう。
そんな時代に私たちは生きているのです。
高齢者の治療の是非、高額療養費制度の見直しなど、議論の対象になっているように、高齢者にも、病気の人にも、苦しい現実です。
3.「今すぐ」できることはあるのか
この厳しい現実の中で、私たち家族にできることは何かを探しています。
結論から言えば、支出の見直しと、使える制度の徹底活用しかありません。
1. 請求書の内訳を「解剖」する
なぜ値上がりしたのかを正確に把握することです。
ケアマネさんが他の施設の値上がりで、多くの家族がやるようになったことを教えてくれたのですが、それが「おむつの持ち込み」。
施設側が用意してくれるおむつを自分で購入し持ち込むことで、おむつの実費だけになるそうです。購入する際、ポイントを貯めることが後に還元できるので良い。
歯ブラシや歯磨き粉などもそうです。
洗濯も自宅でやるようにした人も多いそうです。
ただし、施設によってはNGなこともあるらしいので、そこは確認が必要です。
2. ケアマネさんに「相談」
ケアマネージャーに、金額面について話し、相談にのってもらいます。
介護のプロなので、他の人の事例も含めて教えてくれることもあり参考にできます。
代替できるサービスはないかなど、一緒に考えてもらえます。
他の施設利用料なども詳しいので、本意ではないにしろ施設移動も視野に入れなければならないかもしれません。
3. 公的制度をもう一度調べ直す
もしかしたら手続きもれしているものがあるかもしれません。
対象範囲が広がって対象になっていることもあるかもしれません。
いずれにせよ、現在の制度を自分で調べる、もしくはケアマネさんに教わる、役所で聞いてみるなどです。
制度は、知っているか知らないかで、負担額が変わることも珍しくありません。
まとめ
同じ施設の家族の方は、「自分が何かひとつ節約してみる」と言っていました。
微々たるものかもしれませんが、やってみることは良いことだと思います。
介護施設の突然の値上げは、私たちの心と家計に大きな打撃を与えます。
この先も続くのではないかと不安の一途でありますが、高齢者や病気を抱えた方の命を粗末にするような世の中にならないよう祈るばかりです。
他の記事はこちらから…介護記事一覧
