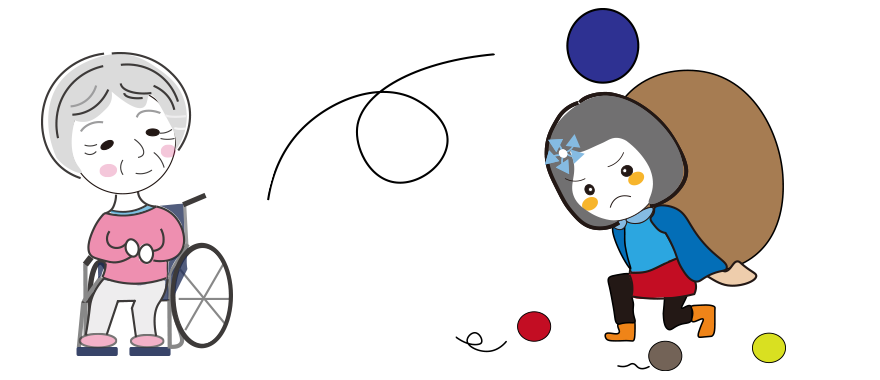
難病介護10年超えのリアル|大脳皮質基底核変性症診断前後に変えた「母との向き合い方」
今年も特定医療費助成制度の更新手続きをしました。
今回で7回目のこと。
この大脳皮質基底核変性症との付き合いは
何なのかわからずにモヤモヤ過ごしてきた診断前の数年の苦しさを含めると10年をゆうに超えることになります。
母が症状を訴えるようになってから診断されるまでの間、
これが私にとってとても苦労した時期ですが、
診断されてから、母に向けて私なりに考えて行ってきたことがあります。
それは簡単にいえば「母とともに」というスタイルへの変更です。
このページでは難病だからこそ、介護される必要があるからこその心の持ち方について、記録します。
1.診断されるまでの暗黒時代
母の右手に現れた「よくわからない感覚(自分の手ではないような、そしてとても痛い)」。
「右手が痛くて包丁が握れないから料理できない」
これはのちに大脳皮質基底核変性症の症状のひとつだと知って、当然の訴えだと知ることになるのですが、
その当時「気の迷い」「怠け」「嘘に違いない」…誰にも理解されず、医療機関ですら「気の迷い、考えすぎ」と片づけられたあの頃。
包括支援センターの人さえ、「母は注意を引きたいから言っているのでは」と疑い、私は母のしつこい苦しみの訴えを相手にしないようにしていたこともありました。
そんな中で母は娘ならば理解してくれるはずと強く思ったのでしょう。
理解できない私に刃のような言葉を浴びせ続けました。
それは、苦しさの矛先が「私」へ向いていたから。
その期間を振り返ると、まさに母と私が真っ向から向き合っていた時期だったのだと思います。
そして、ついに医師から告げられた言葉――
「大脳皮質基底核変性症という病気です」
「やっと終わった」
病気の恐ろしさよりも、不謹慎さよりも、疑念が晴れた安堵と、真実が見えたことで救われたような気持ちになったその瞬間は、今も忘れられません。
2.チェンジするチャレンジ時期
診断直後の「高揚感」や「解放感」はすぐに、不安と心配へと置き換わりました。
「私はできない、私の生活はどうなるの?」
「娘なら親の面倒を見るのは当然でしょ?」
「娘なら仕事を辞めて付き添うのが当たり前でしょ?」
母自身が未来の生活にとらわれる中、不安を吐き続け、私は苦しい中、このままではいけないと視点を変える決意をしました。
それは
「娘として」ではなく、「介護者として」役割を全うするというチャレンジです。
「母は介護される人、私は介護する人になる」
娘だと思うととても腹が立つ言葉も、その感情を横に置いておくことを心掛けるようにしました。
立ち位置を意識することで、できる限り、感情に流されず冷静に対応できるように意識するようにしました。
3.「いまを実感すること」が最も大切
母の数々の言動から、母は「幸せ」や「満足」を実感できない状態だったことに気がつきました。
それは、この病気ならではの鬱傾向からくるのかもしれないし、
治らない病気に対して大きな不安があったからかもしれないし、
自分の不調に対して誰も信じてくれなかったことが原因になったのかもしれません。
努力家だった母が、できなくなった現実に不満を抱え、自分の代わりに力を貸してくれた周囲さえも責めてしまう…
そして、一番良くないのはそれに気づいていなことでした。
悪気なくやっているように感じたのです。
そこで私は極力言い換えることにしました。
「外に私はひとりで出ることができない」と言われたら
→「この部屋、太陽の日差しが入って明るくて気持ち良いね」
「おやつ時間に呼ばれるのが面倒」
→「おやつってほっと一息できる時間だよね」
「本当は寝る前にお風呂に入りたい」
→「朝風呂なんて温泉みたい、朝からさっぱりするよね」
「ご飯まずい」
→「右手が痛いから代わりに作ってくれて助かるね」
などです。
言葉を言い換えるのには正直苦労しましたが、
プラスの言葉を探し続けました。
「ご飯自分で食べる力があるなら、私おいしいもの買ってくるね」
「お母さんの好きなもの、ほんと美味しいよね」
「私、今日も(!)来たよ、昨日も会ったね」
「お母さんの関係で出会う人は良い人ばかり。お母さんが良い人だからだね」
「おいしいね」
「幸せだね」
「うれしいね」
――プラスに感じる感情を見つけて言葉にしてみる――
「日常の幸せ見つけ」をしていくことが私のタスクになりました。
まとめ
難病との向き合いや介護の仕方は、誰にも明確な答えがありません。
介護の現場では意見の相違でぶつかり合うことも多く、ときには相手を深く傷つけることもあります。
それでも介護をすると決めた以上、
娘としての気持ちを抱えつつ、「介護者」としての役割を遂行する――
そのバランスを取ることが毎日を送る(過ごす)ことなのです。
最初はうまくいかないことが多く、母の反発もありましたが、母と同じ方向を向くスタイル「母とともに」へ、徐々に、そして自然に変わっていきました。
コーヒーを飲んで「おいしい」と言い、
ケーキを口にして「食べた(食べれた)」と言い、
そして
母が話すことができた最後の言葉は「ありがとう」でした。
「いまできることは小さな幸せなんだ」という事実が腹落ちできること。
人生の終盤になればなるほど、「人に認められたい」などの欲はなくなり、今あることに目を向けるようになり、その充足感が生きている上でとても大事になってくるのだと、母や母の周りのいる高齢者を見ていると感じています。
他の記事はこちらから…介護記事一覧
